

発足から3年目を迎えたAug Labは、共同研究を通して、新しいWell-beingのあり方を追求中だ。長年パナソニックが培ってきたロボティクス技術による自動化や高度化が、主に課題解決の手法として研鑽を続けてきたことに対し、Aug Labは社内外の垣根を超えたクリエイターたちの参画によって、新たな問いをつくる試みを行なっている。 はたして技術の力を借り、個々人が内包したままの可能性を拡張できると、新たな余白はどのように立ち現れるのだろうか。
Aug Labの共創パートナーである慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科の南澤孝太教授と、ギリシャで建築学を学んだ後、同大学院に進学したHarry Krekoukiotis(ハリー・クレクキョティス)さんは、人と空間が緩やかに一体化する“うごめく壁”、「Spatial Animacy(スペーシアル アニマシー)」をAug Labと共同で制作。 2021年6月、東京・六本木で開催された「Media Ambition Tokyo 2021」での出展を終えたおふたりに、「Spatial Animacy」の制作に至る背景や、未来に向けた実装の可能性などを聞いた。
インタビュー:西村勇哉(NPO法人ミラツク代表)

Spatial Animacyの前にて、南澤孝太教授(写真左)とHarry Krekoukiotisさん(中央)
「Spatial Animacy」のはじまり
西村さん:「Spatial Animacy」に関して改めて概要や、どうしてこういう作品をつくるに至ったかなど、お聞かせください。
ハリーさん:わたし自身は元々、建築と映像を学んできました。それらの知見を基盤にして、現在はデジタルとフィジカル(身体)を繋ぐことに取り組んでいます。「Augmented materiality(オーグメンテッド・マテリアリティ)」と呼び、あらゆる建築素材が拡張していく概念を研究しています。
「Spatial Animacy」では、デジタルとフィジカルの世界を行き来することが途切れずシームレスに行われた時、人の感情がどのように動くのか、あるいは、人のWell-beingがどう高まるかといった、動きのあるものに対する人の共感性について考えました。わたしたちは、生き物が動いている様子を見て、それが「生きている」と感じ取り、親しみや共感を抱くからです。そこで、本来なら動かない構造物や物が、人の感情に反応して動き出すとしたら、そこにわたしたちはやはり共感性を抱くのではないか、という問いを立てて探究を始めました。
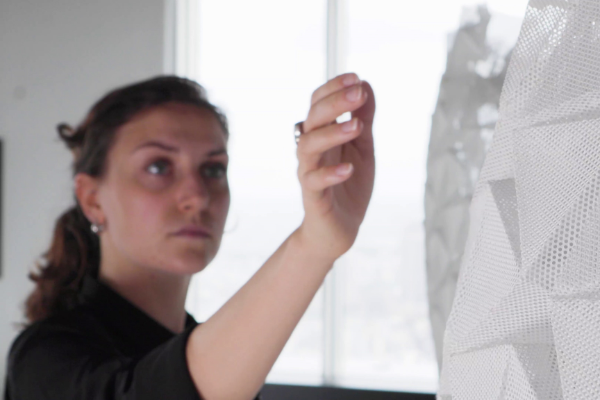
ハリーさん:どのような手法で建築空間を動かすのがいいだろうかと考えて着目したのが、折り紙の構造でした。折ることによって縮んだり広がったりするダイナミクスな動きが出せるようになり、さらにたくさん繋ぐことで大きなサイズのものがつくれるからです。 素材も「Material driven design(マテリアル ドリブン デザイン)」という、素材に触発されるデザイン手法を選択しました。「Spatial Animacy」の前に立つ人と双方向に呼応するためには、素材はとても重要なものだと捉えたからです。実際には、メッシュ状の化学繊維を使い、1枚の大きなシートを折り紙の構造通りに折ってつくりました。
南澤さん:インタラクティブなデザインを、素材をベースにしてつくるというのは確かに興味深かったですね。
身体で感じる、デジタル情報
西村さん:この形や動きにはどのような意味などが込められているのでしょうか? 平らな壁にしなかった理由もお聞かせください。
ハリーさん:現代社会に生きるわたしたちは、日々スマートフォンやインターネットといったデジタルテクノロジーを使い、もうほとんどデジタルの世界の中で動いていると言っても過言ではありません。しかし実体験は今も、それぞれの身体(しんたい)を通して得ているわけです。「デジタルな世界」と「体でデジタル情報を感じること」の2つを繋げることは、今後ますます重要な要素となっていくでしょう。
すでに、デジタル情報を身体的な経験に落とし込む研究は進んでいますが、今回はそれを、「空間を動かす」ことによって実現しようとしたんです。デジタルテクノロジーによって生み出される情報を、人間にとって自然で直感的に、経験として取り込みやすいものに変える。それが「Spatial Animacy」のプロジェクトにおける本質的なゴールだと考えています。

ハリーさん:「Spatial Animacy」の表面がうねる動き自体は、背面に取り付けたアクチュエーターという機動装置によって可能となり、同時に、周辺の人の動きを測っています。人が近づいてくると、表面からの距離や位置に応じて「Spatial Animacy」が動き始めます。まるで生物のような、もしくはそれの呼吸のような動きで、その場にいる人との関係性をつくろうと試みるのです。
制作当初は、完全にフラットな壁をつくろうとしていたんですが、コンセプトに立ち返り、より有機的で生物的な形となりました。構造物が生き物的な生命感を持ち、呼吸するように膨らんでは縮む、自然で無理のない動きを出すことができたと思っています。
動きによる生命感をより大切にするために、模様や飾りも一切排除し、真っ白にしました。極力ニュートラルでまっさらな状態で、動きだけを感じてもらうためです。
南澤さん:そうしたことの結果、「Spatial Animacy」の見た目は、内臓というか人の胴体のような、丸みやくびれなどをイメージできるものとなりました。動かずに止まっていたとしても、ちょっと生命感があるフォルムです。人が近付いてきてスイッチが入り、呼吸のような動きをし始めると小さな振動もあり、それはどこか、クスクスと笑っているような姿をも連想させます。

南澤さん:僕らは元々「Embodied Media(エンボディードメディア/身体性メディア)」という、「身体」のスケールでいろんな研究をしてきました。何かを身につけたりすることで見える世界を変えたり、体の感覚に着目しています。Aug Labのテーマの中に「空間」があったため、僕らにとっても「身体」から「空間」にチャレンジする機会となりました。
西村さん:なるほど、南澤さんたちにとっての実現したいことと、状況における制約条件、両方がうまく同じところに辿り着いてくれた、ということですね。
南澤さん:そうですね、結果としてすごくオーガニックなものにできたと思います。特に、僕自身が自分も体験してみて、壁と呼吸を合わせる面白さを感じました。そこで、展示会場が決まって初めて、このスケール感、つまり壁としてのサイズもこの大きさにしよう、と決めたんです。壁の呼吸に自分の呼吸を合わせていくと、まるで自分の呼吸が可視化されたような、壁と一心同体になったような感覚を実感できるのですが、その時、壁のように自分の視界をすべて覆うサイズであることが重要です。
もしも「Spatial Animacy」が自分よりも小さいサイズだった場合、人は自分事に寄せ切れず、自分とはまた別の存在がそこにある、と認識するでしょう。しかし、それが空間を占めて視界いっぱいに広がるサイズであれば、呼吸のたびに近距離に感じ、また動くたびに近づいてくるように感じられます。まるで包み込まれるというか、もしかしたら、子宮の中みたいな感覚や、あるいは、自分自身を内側からクルッとひっくり返して外側から見ているとか、そういった一体感を感じてもらえると思います。もしかしたら、自分が自分の中にいて、それを見ているような感覚を覚えるかもしれません。
ハリーさん:建築家の視点からも、人の身体より小さいか大きいかというスケール感は大切な要素だと考えています。人の身体より小さいと、それは「自分の目の前に存在しているもの」であり、反対に自分の身体よりも大きいスケールならば、それは「自分を囲っている回りの空間」になる。その際の経験や体感も、ある意味では支配されたものになるんですね。

何もない間(ま)にあるもの
西村さん:構造物を動かす本意は、空間にあるものをデザインする、ということなんですね。
ハリーさん:空間を考えている時に興味をもったのは、日本における空間の「間(ま)」の考え方でした。「間」は、人と建築物とのあいだにある、「何も無い空間」のことです。実際には空気があるだけ。でも、人との関係性は存在するんですよね。人と空間の「間」をつなぐデザインを考えることは、とても面白い考え方です。なぜなら、何も無いだけではなく、そこには「時間」という存在もあるからです。
人と空間、人と環境とのあいだで影響を及ぼし合う時、反響はどのくらいの時間で届き、また、どのくらい反射するのか。2者の関係性がどういう時間的スケールで築かれていくか、といったことを考えると「間」は大変興味深い要素です。
西村さん:神殿などに象徴されるように、本来の建築は一般的に普遍という価値があったと思うんですが、今はそれとは全然違うものをつくっているわけですよね。そこで建築を変えるというよりも、今までなかったものを新しくつくっている、と。
南澤さん:そうですね。海外から来たハリーは、とても強く面白さを感じるようなんですが、神社やお寺、森といった自然が豊かに残る空間で感じる生命感のようのものって、ありますよね。八百万(やおよろず)の神のような、あらゆるものに神が存在する考え方を、やはり日本人的の伝統的な感覚として持っている一面があるように思います。僕らがその辺の花や木、あるいは風といったものが生きていると感じるこの感覚も、テクノロジーの登場でもう1回再構築されて、デザインし直すことができるんじゃないか、というアイディアをハリーから聞いた時は、非常に面白いと思いました。
木とか森とか建物といったものに生命感を感じる感性を、デジタルテクノロジーと組み合わせることで、今回のように壁とか、あるいは柱などの建築物そのものにも命を感じるようになる。一種のエンパシーが生み出せたら、普段の暮らしのそこかしこに温かみが生まれてくるんじゃないか、という考え方です。実際、現代の僕らの暮らしは生命のない冷たいものに囲まれているわけですから。この発想はやはり海外から日本を捉えた見方ならではですし、日本の、ある種の感性的なところを再構築したという意味でも面白いと思います。

動きのある未来の暮らしの姿
西村さん:いつかこの壁ができて、さらに発展して実際の暮らしに実装された未来を想像した時に、生活はどう変わっていくとお考えですか。きっと、何か新しい生活の価値や様式が生まれてくるように思うのですが。
南澤さん:いわゆるUX(ユーザーエクスペリエンス)とUI(ユーザーインターフェイス)を建築で考えると、住んでいる人たちの生活や経験がUX、そして空間そのもののデザインがUIになるわけですが、そこにいかにテクノロジーを持ち込むか。それがおそらく新しい取り組みであり、チャレンジになっていくと考えています。
空間や建築物といった本来なら動かないものが「animacy(有生性)」を持つとどうなるのか、そのテーマで突き詰めていくと、UXも自ずと変わってくることでしょう。例えばAIBOとかASIMOとか、本来生きていないロボットや電子機器とかガジェットに、生きている感覚を感じること自体が、日本ならではの特徴でもあるんですね。人と空間との関係性がこれから大きく変わってくること、それこそがこの研究の非常に面白いところでしょう。
ハリーさん:わたしたちは日々のデジタル情報を、パソコンやスマートフォンというスクリーン越しに見ていますよね。SF映画で描かれる未来も、物理的であれサイバーであれ、あらゆるものをスクリーン上で見ている世界線ですが、果たしてそれは本当にわたしたちが欲しい未来かと問われると、どうでしょうか。
デジタル情報を得るためにスクリーンを見ている時、周囲との関係性は断絶されてしまいます。すでにわたしたちは、個々人があちこちで使っているという意味で、巨大なスクリーンに囚われているとも言えるでしょう。
それならば、未来はむしろスクリーンが無い世界が望ましいのではないでしょうか。デジタル情報が自然な形で、身の回りの環境や空間に埋め込まれていて、スマホやスクリーンに釘付けにならずとも、環境の方からわたしたちに歩み寄り、必要な情報を手に入れることができるとしたら。それこそが、デジタルとフィジカルがつながる未来ではないでしょうか。

南澤さん:今もすでに、スクリーンやデジタルガジェットを減らす研究領域はあるんですよね。より自然で人に馴染みやすいテクノロジーのあり方を研究している人たちです。今僕らが考えている新しい建築のあり方や生活環境に対するエンパシーも、そうした研究者たちに貢献できる可能性があります。
僕ら自身、「身体性メディア」というコンセプトで研究を続けているので、身体で感じる経験はこれからも大事なものとして捉えたいです。それこそSF映画では、脳みそがマシンとつながっていたり、体を動かさずに頭の中で経験を得るような描き方をされますが、もしもそうなった時、本当に幸せになれるのかと考えたら、多分そうではないと思うんです。とはいえ、あらゆるテクノロジーやインターネットから離れて生活したいというわけでもない。
今大切なのは、いかに自分たちのこの身体と感覚を大事にしながら、同時に、自分たちが住んでる都市や町といった環境をどう捉えるか。特に、デジタルな空間やテクノロジーの存在を前提にした上で再構築を考える必要があります。そうしないと、情報だけが溢れて、情報に使われる、または情報に流されるような暮らしになってしまうんじゃないかと危惧しています。
改めて身体的な感覚とか、自分の肉体で感じる経験を取り戻すためにも、人と情報技術の関わり方を捉え直そうよ、ということも「Spatial Animacy」のプロジェクトで大事にしているコンセプトです。

エンジニアリングで生命感を知る意味
西村さん:今の話とも関連すると思うんですが、エンジニアリングで生命感を知る、その意味についてもう少し聞かせてもらえますか。例えば、動物を連れてくるとか獣の皮を展示するわけではなく、機械工学でする意味みたいなことについて。
ハリーさん:例えばバイオ工学で細胞を培養して新生命の形や動く心臓をつくる、あるいは、人型や動物型ロボットの研究者たちが形と機能によって生命感を出そうとするなど、生命感の再現はこれまでもされてきたことです。
僕らの取り組みでは、あえて違うアプローチをとっていて、例えば非常に抽象的な形を選びました。これが生命ですよと示せずとも、動きや質感やデザインによって生命感を感じられるかどうか。呼吸やクスクスと笑う感じ、あるいは心臓の鼓動のようなものを感じ取れるかどうか。抽象的な形をした三次元的な存在が、動きだけで生命感を感じさせるかどうか。人が感じる動きに対するエンパシーの本質を知ることも目指しているところです。
南澤さん:例えば「四つ足であれば動物だ」とか「これは花だ」といった、情報や知識として知っていることがありますが、「犬の形をしているから犬だ」と思うことと、「犬の形はわからないけど、そこにある温もりや呼吸の感じが命だ」と感じることは、実は後者の方が本質的な生命に対する共感だと思うんです。
生きている相手を、鼓動や温もりで感じ取るわけで、それは例えば目が見えていなくても感じることですよね。今回の僕らの研究でも、視覚に障がいがある方にも参加していただければと思っていたのでが、今回はコロナ禍ということもあって、そうした試みは難しくなってしまいました。
ただこれまでの経験から言うと、目の見えない方も、おそらく白杖を使わなくとも壁の前で止まることができると思います。音の反響や風の流れの変化を敏感に読み取って環境を認識されているからです。状況が許されるようになったら、ぜひそうした方々にも体験いただきたいです。
西村さん:最近の研究などで、記憶はものに反応した情報が引き出ているのではなく、空間と紐づいていると聞きます。だからその空間に身を置かないと出てこない記憶もあると聞いたことがあるのですが、その意味で今回のプロジェクトは、空間を扱えることに大きな強みがありますね。ものとは違う、記憶のあり方もつくっていると思いました。
南澤さん:そうですね。多分、それは結局人の脳や心への働きかけ方が、ものに接する時と空間に接する時で違うからなんですね。ものに接する時はやはり人が意識的に接するわけです。例えばこれを「どう扱う」とか「何に使う」とか、能動的にアプローチするものです。しかし空間は、そこに自分も存在している以上、本質的には受動的にアプローチするものです。僕らはみんな、ある意味で場所に対して受け身で存在するわけですね。
でも、空間自体が人に関わりをもってくると、人はそれに対しても受身的に受け入れざるを得ない状況となり、双方向のインタラクションも新しい形になってくるかもしれませんね。

「Media Ambition Tokyo」での出展を終えて
西村さん:先日、六本木で「Media Ambition Tokyo2021」の出展を終えたばかりですが、アート作品と一緒にあの場に並び、来場者に体験してもらえたことについては、どんな感想をお持ちですか。
南澤さん:「Media Ambition Tokyo」は単にメディアアートを置く展示会とも異なり、都市とメディアアートの関わりを考えている展示会でもあります。僕らも建築や構造物など、空間をデザインすることを基点にしている以上、最終的には都市のビルや居住空間、商業空間といった所に入っていけることを考えてもいるので、今回出展できたことは、都市部における「Spatial Animacy」のようなものの存在価値を考え直すきっかけになりました。
また、都市開発や都市デザインをされている方々に向けても可能性を示せたのではないかと思っています。鉄骨や壁にも、人と関わりながら生命を持つ可能性があると知ってもらうことで、設計する前提が変わり、新しい議論を始めるひとつのきっかけになれるとしたら、出展できた価値は非常に大きいですよね。
ハリーさん:最近、学会でもこういったアート展という形での発表も増えています。研究者がサイエンスやテクノロジーいった手段で研究を進めるのは「課題解決」のためであり、アートやメディアアートは「問題を提示する」役割をしていますよね。
問題の「提示」と「解決」の両方が混じり合うことによって、今までとは違う視点からの可能性や気づき、新しい意見などを様々な分野の人から受けることができました。最近いろんなところでサイエンス&テクノロジーと、アーバンデザインといった交流が進んでいるのも、こうした気づきを重要だと捉えていることが理由だと思います。
アートの世界にいる方々にとっても、50年先の技術かもしれないような科学の話が作品のインスピレーションになるかもしれないし、問題設定や問題定義のきっかけになるかもしれません。そして研究者にとっては、アートから提示された問題定義が、50年後、100年後にどういう新技術や新しい科学をつくっていくべきかを考えさせてくれます。
西村さん:面白いですね。結果として、生命感から始まっているものが未来への都市の提起になっている。
南澤さん:そこから新しい空間、例えば住む場所はどうデザインできるか、さらには、ライフスタイルはどうデザインし直せるのか、新しい建物とか町とか公園といったパブリックスペースのあり方を考え直すことにつながるでしょうね。バーチャルとフィジカルがハイブリッドになる社会の中で、その間をつなぐ手段は、すでにいろんな議論が始まりそうなところまで来ています。
奇しくもコロナ禍になったことで誰もが自宅にいる時間が増えて、身の回りの空間とか環境に対する意識も変わりつつありますよね。おそらく人類全体、社会全体として、空間を捉え直す問題提起が発生したわけです。
せっかくならここから、もっと空間をフレキシブルに、生活の心地良さとか安心感とつながるようなものにしたいですよね。ひとりで1Kのワンルームの全部白い壁の中にいるよりも、「Spatial Animacy」のような、時々こちらに反応してくれる空間に行った方が心が安らぐとか安心するとしたら、それはWell-beingでもありますから。

Aug Labの今後に期待すること
西村さん:今回はAug Labでの共同研究ということになりましたが、実際に参加されて感じたことや、これから期待されていることなどありますか?
ハリーさん:イノベーションのためには企業側も大学側も、お互い自分の領域から飛び出して、いろんなアイディアを交わすことが大事だと考えています。そんな理想的でオープンな環境を、パナソニックという大企業がつくってくれたことは、今回本当に驚いたことでもありました。しかも、パナソニックならロボット的なことを追求するのかなと思ったら、
テーマはWell-beingだという。
期待を上回る問題設定をしていることと、そこにいろんなコミュニティや大学、スタートアップといったチームが加わり、パナソニックという大きな組織からの視点とは違う視点を取り入れようと努めることがすごいと思いました。
参加させていただいているわたしたちにとっても、新しい視点や問題設定を得ることができますし、また同時にパナソニックにとっても、新しいことを進める上で大事なことだと捉えてらっしゃるんだと思います。こうしたところからイノベーションが始まるんですね。
南澤さん:今回僕らにとって非常に大きかったのが、これまで身体性を追求してきたところから、空間におけるWell-beingにチャレンジするきっかけをいただいたことです。
僕らがつくってきたものは、時間で言うと3分とか3秒とか、長くても30分くらいの体験でした。しかしパナソニックさんがつくる家電や住宅や自動車は、時間のスケールが全然違いますよね。1回買ったら10年、20年、家なら30年だって住むことがある。
3分と3年では、ゼロが6桁分くらいスケールが違ってきます。パナソニックがつくる製品は10年は使えないとユーザーには怒られるわけですが、わたしたちが普段作る研究デモンストレーションは、3分で理解ができないと伝わらないわけです。パナソニックってそういうものをつくってる会社なんだよな、ということを改めて感じましたし、これほど異なるスケールでものをつくっている両者が、お互いに対して違う問題設定を提示できていること自体がすごく面白いですね。
ただ今回どうしてもコロナ禍の影響があって、思うように議論を深めたり、一緒に何かをつくるという機会が持ち切れなかったことだけは残念に思っています。
西村さん:ありがとうございました。では最後に、パナソニック安藤さんから、今回の振り返りについてお聞かせください。
安藤:ありがとうございます。「Spatial Animacy」は共同研究プロジェクトの第1弾ということになりました。期間にして約1年半ぐらいでしたが、まずお伝えしたいのは、素晴らしい作品を生み出してくださったことに対する感謝の気持ちです。
途中からコロナ禍の影響があったものの、最初は南澤先生の学生さんもいっぱい来ていただき、ワークショップもさせてもらうことができました。特にパナソニックとして最も喜ばしいことは、プロダクトしかつくってこなかったわたしたちが、仲間たちと共に「将来は空間がどういうものになっていくのか」といった議論をさせてもらえたことです。
特に最近のパナソニックはどうしても、いかに機能的なプロダクトをつくり、それをどうやって広めるかという目的のために空間の機能を考えてきたわけですが、機能以外の空間の価値を捉える機会になりました。中でも、人と空間の関係性についてディスカッションさせていただいたことは、わたしたちにとっても非常に大きな財産になったと思います。ありがとうございました。
西村さん:ありがとうございます。聞いていて思ったんですが、昔パナソニックは電球をつくったわけですよね。電球がない世界から電球がある世界に移ったという意味で、空間のあり様をものすごく変えましたよね。機能面はもちろんですが、感覚的にもものすごく大事な価値観をつくったと思います。それまでは下から明かりが照らされていた生活が、頭上から明るくなった生活に変わったわけですし。
パナソニックのすることがより機能面に特化していったのかもしれませんが、御社がこれまでやってきたことの中には、実は感覚的なこともたくさん、無意識的にやってきたようにも思っていて、Aug Labもそうした、意識的にやり直すみたいなことに戻っていく流れを感じました。ありがとうございました。
*
本記事で紹介しています「Spatial Animacy」は下記URLでも紹介しております。
Spatial Animacy
また、プロジェクト開始時の記事は下記URLで紹介しております。
“空間と人との関係性を変える”ことにチャレンジしたい
