【6月EX Monthly Meetupレポート】
都市の創造性はいかにして育まれるか?〜オーストリア・リンツ編〜

「スマートシティ(街)をどう実現していくかより、スマートシチズン(市民)をどう育成していくかを考える方が大事だ」━━。
去る2017年。東京オリンピックを3年後に控えた日本で、ある有識者の提言が都市計画に大きな影響を与えました。「灰色の鋼鉄の街」だったオーストラリアのリンツ市を、世界屈指の文化芸術都市として再興させたメディアアートの祭典、「アルスエレクトロニカ」の総合芸術監督を務めたゲルフリート・ストッカー氏その人です。
以来、技術・テクノロジー偏重だった国内の都市計画は大きく方針を転換。都市本来の機能であり目的である、「『人』のために街をつくる」という考え方へとシフトしました。
2025年6月のMonthlyMeetup、テーマは「未来の社会づくり」。上記のオーストリア・リンツ市におけるまちづくりの事例から、技術未来ビジョンが目指す「共創・共助社会」の在り方を学びます。ゲストスピーカーは、アルスエレクトロニカと博報堂のクリエイティブ・プラットフォームのプロジェクトリーダーである鷲尾 和彦さん。
本稿では、当日の学びと交流の様子を、会場の熱量そのままにお伝えします。
イベント詳細
EX革新活動をするメンバー同士が活動を共に振返り、フィードバックをし合い、新たな学びの視点を持つことで、今後の活動を加速させることを目的として立ち上がった学びの共有の場。現在はより柔軟に形を変え、社内外の知見を組み合わせることで、新たな共創の形を生み出すことを目的とした、テーマ型のオムニバス形式の勉強交流会へと成長しています。
2025年6月度のテーマは「未来の社会づくり」。オーストリアのリンツ市とスペインのバスク地方、2つの都市それぞれの事例から、未来社会をデザインするヒントを探りました。
登壇者紹介

鷲尾 和彦(わしお かずひこ)
株式会社博報堂・クリエイティブビジネスプロデューサー、株式会社SIGNING(博報堂DYグループ)チーフリサーチディレクター。現在、「文化と経済」「都市/生活圏」をテーマに、戦略コンサルティング、クリエイティブ・ディレクション、新規事業開発などで、民間企業、自治体、国際機関、NGO等とのプロジェクトに従事。主な著書に『共感ブランディング』(講談社)、『アルスエレクトロニカの挑戦』(学芸出版社)、『CITY BY ALL ~生きる場所をともにつくる』(博報堂生活総合研究所)、『カルチュラル・コンピテンシー』(Bootleg, 共著)、『クリエイティブ・ジャパン戦略』(白桃書房, 共著)等。
「灰色の鉄鋼の街」から、世界屈指の文化芸術都市へ。

MonthlyMeetup当日、会場であるEXLには多数の参加者が来場しました。所属はパナソニックをはじめ、門真市役所や京阪ホールディングス株式会社など、さまざま。共通するのは、「まちづくり・地方創生」「共創社会」といったキーワードに対する強い興味関心です。開始時刻になるまで、それぞれが積極的に交流し、取り組みを紹介し合う様子から、今回のイベントに対する高い期待感がうかがえました。
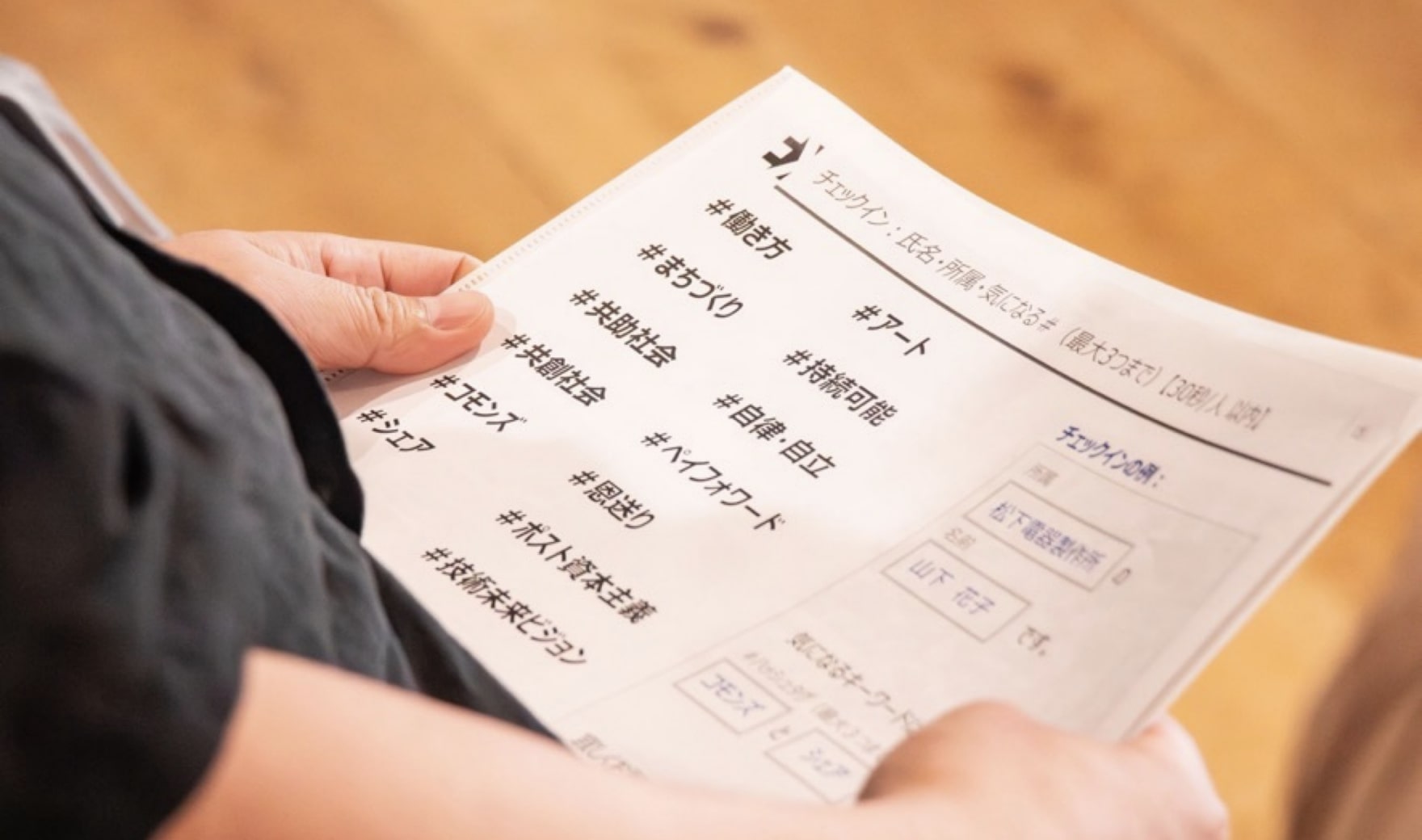
ゲストの鷲尾さんよりご挨拶と自己紹介を皮切りに、いよいよイベントがスタート。氏は博報堂DYホールディングスの100%出資会社である株式会社SIGNINGに在籍しており、世界各地の街の風景から新しい社会の“兆し”を捉え、より良い社会への道標をつくるべく、街の調査・リサーチや研究、レポートの制作・発信を手掛けています。
今回焦点を当てた街の風景は、オーストリアのリンツ市。毎年9月に開かれる世界最大級のメディアアートの祭典「アルスエレクトロニカ」の開催地です。今でこそ文化芸術都市として知られるリンツ市ですが、一昔前までは鉄鋼業の街として栄えた「灰色の街」でした。鷲尾さんはリンツ市が今のような街になった経緯について、歴史を振り返りながら次のように説明します。
「リンツ市は、観光名所に恵まれた周辺のウィーンやザルツブルグと違い、田園地帯が広がっていたり漁村があったりと、働いている人たちの街でした。最初の転機となったのは第二次世界大戦です。同地域はかのアドルフ・ヒトラーの出身地であり、大戦中にナチスによる軍事占領の下、鉄鋼業が栄え、都市の近代化が進みます。しかし、1970年代以降はポスト工業社会を迎え、鉄鋼業は不況に陥りました。それに伴い街もどんどん衰退していきます」。

鷲尾さんは、「街の歴史はつながっているため、一部分を切り取って『ここから変わった』とは明確に言えない」としつつも、工業都市として栄えたリンツ市がポスト工業社会へと舵を切ったタイミングが、まさにこれからの話す「街の風景が変わり始めた」起点になると、説明を続けます。
「斜陽化する産業に衰退する街。そんな状況下にあった工業都市リンツが再起をかけて取り組んだのが、アート・テクノロジー・社会をキーワードとした祭典『アルスエレクトロニカ』でした」。
暮らしたくなる街をつくる鍵は「人」

工場(生産資本)で都市をつくっていた時代から、人(社会資本)が都市をつくる時代へと移り変わったリンツ市。鷲尾さんの話は、その大きな転換点である「アルスエレクトロニカ」の紹介へと進んでいきます。
氏はまず、現在のアルスエレクトロニカの様子について、写真を交えながら説明し、リンツ市の今の風景を参加者と共有しました。
「アルスエレクトロニカは、ただアート作品を展示しているだけではありません。街の日常空間の中に、アートと出会う体験を豊富に入れ込んでいく形で開催されています。そのため、コンテンツはアート展示に限らず、コンサートやカンファレンス、シンポジウムにワークショップといった、様々なものがあります。著名なアーティストが講演をしている隣で、子ども連れの家族がふらっと立ち寄ってワークショップを楽しんでいる。そんなある種カオスな風景を見られるのがアルスエレクトロニカの特徴です」。
「1980年代半ばからは国際コンペディションも行われ、若い才能を発掘・支援する動きも生まれました。審査員の皆さんはボランティアで、これから社会を変えるかもしれない新しい才能との出会いを求めて参加しています。一方、アーティストや研究者は、自分たちの作品や研究成果に可能性を見出してくれる人たちとの出会いを求めて参加しています」。
現在の街の風景を一通り説明した後、鷲尾さんは今に至るまでの経緯や背景について詳しく紹介しました。
「『アルスエレクトロニカ』は、電子音楽の祭典として1979年の9月に産声を上げました。以来、アート、テクノロジー、そして社会をキーワードに開催され、世界を代表するフェスティバルとなりました。開催当時は懐疑的に見ていた政治家たちも、同フェスティバルに大きな期待を寄せるようになり、以来リンツ市と協力しながら発展していきます」。
文化発展計画において、行政の役割は市民が創造性を発揮しやすいフレームを整備すること。そして何より、カルチャーフィットの点において、生活が大きく変わることに対する市民の恐怖感をポジティブなものに変え、オープンマインドで迎え入れられるようにする意識改革でした。
そのため都市計画においては、施設の整備や拠点の新設といったハード整備だけに偏らず、むしろ教育や啓発・啓蒙といったソフト面に力が注がれています。
「アルスエレクトロニカの期間は1年の中で1週間のみ。それを市民が年中体験できるようにしたいと、さまざまな施設や取り組みが生まれました。代表的な例として、体験型アートセンターである『アルスエレクトロニカ・センター』を紹介します。ここには『インフォトレーナー』と呼ばれるスタッフが常駐しており、来館者とリンツ市、そしてアーティストをつなぐ大きな役割を果たしています」。
鷲尾さんは、センターの運営において、この「インフォトレーナー」の存在がとても重要だと話します。
「未知のテクノロジーに触れたとき、一部の人は恐怖感を覚えます。皆さんも過去にこうした経験があったかもしれません。『インフォトレーナー』は、そうした来館者一人ひとりの体験に寄り添い、対話を行う専門スタッフです。ただ展示している作品を説明するスタッフではありません。目の前の来館者がどのようなバックグラウンドを持ち、目の前のアート作品やテクノロジーと出会ってどのように感じたのか。そこを丁寧にヒアリングし、その人なりの物語を一緒につくっていく専門職なのです」。
来館者のほとんどはリンツ市民。インフォトレーナーは、街をつくっていく当事者である彼らと、「あなたは作品を見てどう感じたか」「あなたなら何ができるか」と丁寧に対話することで、センターを文化教育的な場に昇華しているそうです。
「センターを見ると大小さまざまな機能があり、そこに着目される方が多いのですが、実は一番大事な鍵を握っているのは『インフォトレーナー』、この人たちなんですよ」。
鷲尾さんは講演中「要となるのは『人』だ」と繰り返し訴えており、その強いメッセージは会場に静かに響き渡っていました。
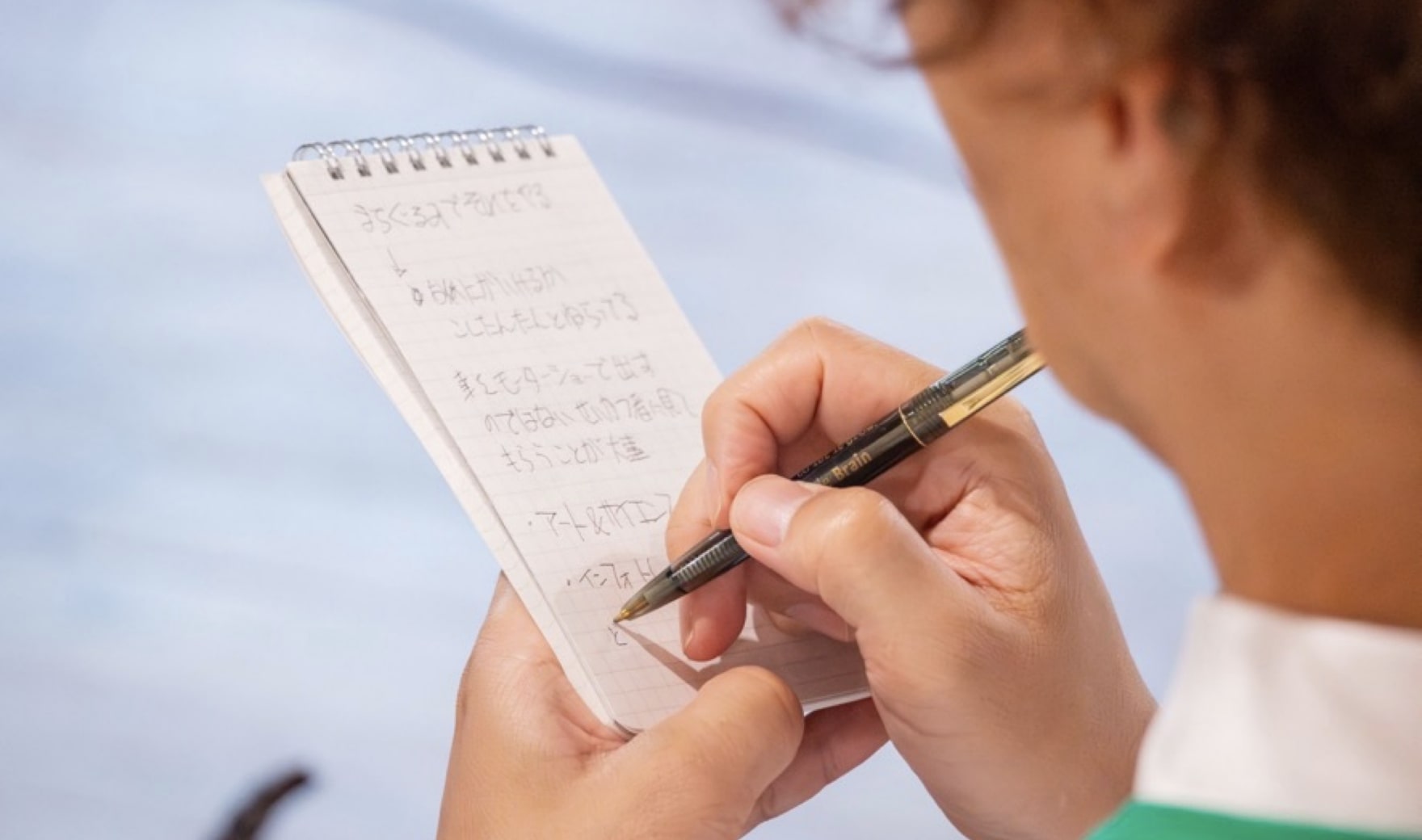
対話を通じた相互理解、その先に未来社会がある
「灰色の鉄鋼の街」から世界屈指の文化芸術都市へと再生したオーストリア・リンツ市。その要となったのは、メディアアートの祭典「アルスエレクトロニカ」に見られる、市民をはじめとする一人ひとりの当事者でした。
鷲尾さんのお話からは、長らくハード偏重だった国内の都市計画への反省と、フェスティバル(祭り)の非日常の力を日常につなげる動線の大切さを学ぶことができました。
また、AIの進化やテクノロジーの急速な発展、それに伴う新しい価値観へのアップデートを迫られる昨今においては、市民一人ひとりとの丁寧な対話が時代を進めるキーファクターであることもわかりました。
技術未来ビションが目指す「共創・共助社会」。新しい文化モデルが誕生する際には、必ず摩擦が生じます。そうしたコンフリクトを乗り越えるために、私たちは対話を通じて相互理解を進めていく必要があるのだと、改めて気付かされたMeetupでした。

商品の販売終了や、組織の変更などにより、最新の情報と異なる場合がありますので、ご了承ください。

未来の働き方サポーターによるこの記事へのコメントを掲載しています。
※この記事へのコメントはまだありません。