「何か面白いものが生まれそう」から始める。
まだ見ぬ未来を共に描く“新たな形の共創”へ。

自分たちだけで描けるゴールには限界がある━━。
これまでの共創は、ゴール設定をし、足りないリソースを補うために内外のステークホルダーと連携する形が主流でした。しかし、それは「リソースさえあれば自前でできる」ことでしかありません。
「我々だけでは描けないゴール、そこにこそ共創の真価がある」という信念のもと、2024年11月、社内においてまさにその"真価"が問われるプロジェクトが発足しました。当初具体的なゴールは無く、きっかけは「何か面白そうなことができそうだったから」。
本稿では、プロジェクトのキーマンであるオープンイノベーション推進部部長の松村さんへのインタビューを通じて、新しい共創の形に迫ります。
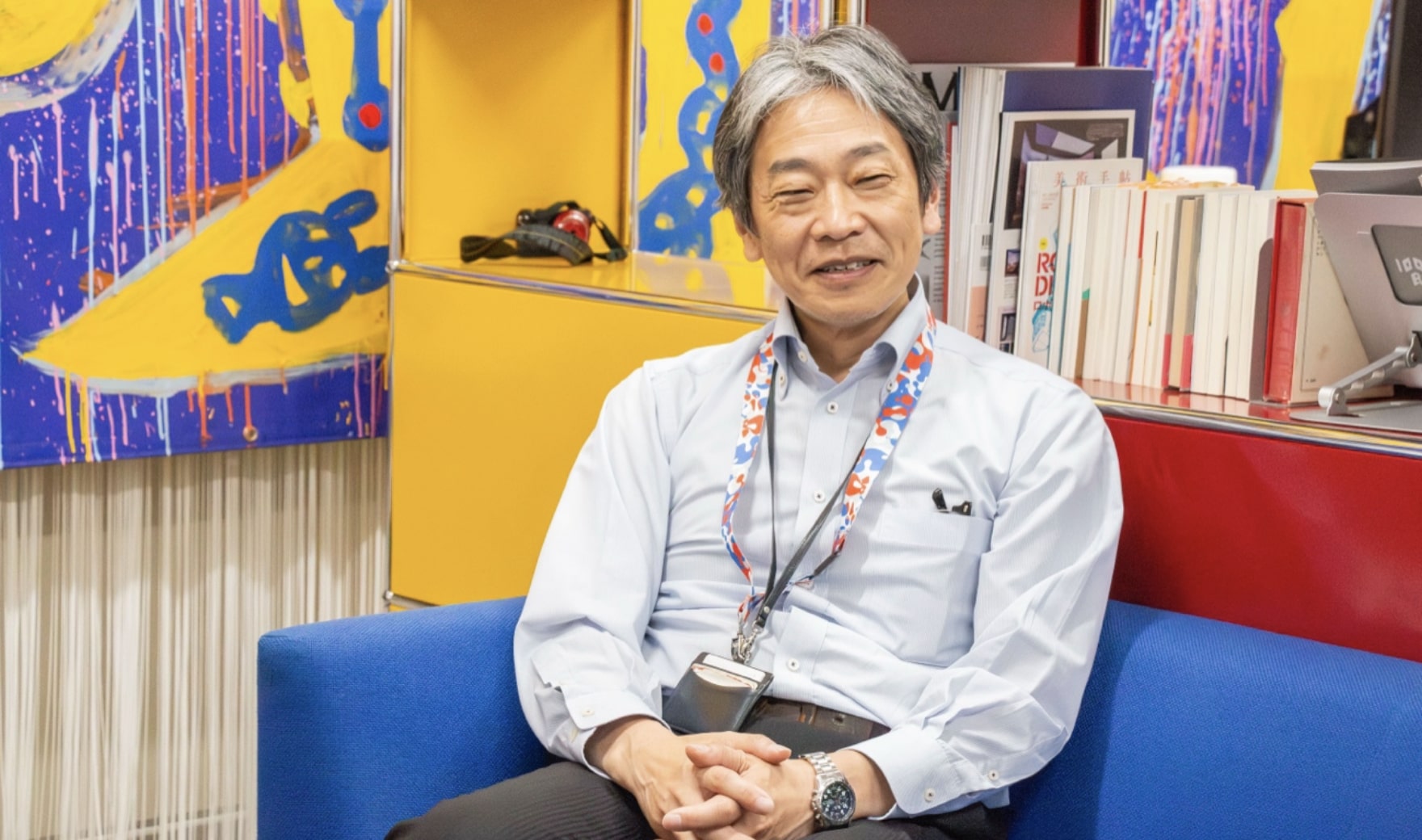
松村 浩一(Matsumura Kouichi)
オープンイノベーション推進部 部長
パナソニックラボラトリー 所長
国立大学法人福井大学 招聘准教授
1994年松下電器産業株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社)入社。初期には研究者としてインターネット黎明期における映像配信技術の開発に携わり、その後、テレビ事業のデジタル化、リテール向け技術開発などを経験。北米のベンチャー企業との共創活動にも関わり、さまざまなスタートアップや海外技術に触れ、その後現職にて産学連携や、社外との協働を進めてきた。2024年より現職。
それは、「何か面白そう」から始まった
「面白い会社があるんだが、一度会ってくれないか」。2023年11月、グループCTOの小川 立夫さんから松村さんに声がかかりました。
「渋谷のイベントで出会った海藻のベンチャー企業が面白くて、実際に商品を食べてみたらとても美味しかったと、小川さんから紹介があったんです。出資や提携の相談かなと思い、じゃあ一度話を聴いてみようということで、企業の集まりに参加しました」。
当初、日本のベンチャー企業にあまり良いイメージを持っていなかったと話す松村さん。「すべてがそうだとは言わないが、上場や出資獲得、売り抜きを目的にしている人たち」との印象が強かったそうです。しかし、その印象は一気に覆りました。
「実際に彼らにお会いしてみると、私の持っていた印象と全然違ったんです。パリッとしたジャケットを羽織ったビジネス然として人ではなく、真っ直ぐに海藻の可能性と魅力を語る純朴な方々でした」。
キラキラした目で事業を説明する彼らの会社は、海藻の陸上養殖を手掛ける合同会社シーベジタブル。磯焼けで減少する海藻を採取・研究し、環境負荷の少ない陸上栽培や海面栽培で蘇らせ、新たな食べ方を提案する高知県発のベンチャー企業です。

「詳しく話を聞くまで知らなかったのですが、国内の藻場は高齢化や人手不足、さらには海水温の上昇といった環境の影響で海藻が無くなり、ほとんど崩壊状態にあるんです。彼らは全国各地に陸上養殖場をつくり、藻場の再生はもちろん地域に雇用を生むことで、そうした課題と闘っていました」。
藻場はさまざまな海の生物の住処や産卵場所になっており、その喪失は生態系を大きく変えてしまうほどの影響力を持っています。シーベジタブルは事業を通じ、そうした藻場の再生や、地域雇用の創出、食文化の保護を行ってきました。
「実際に現地の養殖場に視察へうかがったのですが、ハードな仕事にもかかわらず、若い人や障害のある方がとてもいきいきと働いていて驚きました。正直、この会社は何なのだろうと衝撃を受けましたね。向き合っている課題のレベルが高く、単なるお金儲けじゃない。しっかりと稼ぎながら社会課題の解決に向き合っている人を目の前にして、何かできることはないだろうかと考えるようになりました」。
共に理想を描く、新しい共創の形
シーベジタブルとの出会いから、連携の可能性を模索し始めた松村さん。しかし、ここで大きな壁が立ちはだかります。
「どういった連携が可能か、目線合わせが難しかったです。パナソニックは事業領域が広く大きいだけに、先方からすると我々に何ができるかがわかりにくい。また、技術連携や出資についても、だいたいのことは既に社内で誰かがやっているため、自前でできてしまい、競合になってしまう。どうしたものかと頭を悩ませました」。
これまでの連携の形だと、社内の既存の事業部と摩擦が起きる恐れがある。自前主義からの脱却を掲げてはいるものの、長く社内外の連携を見てきた松村さんは、それが口で言うほど簡単ではないことを身に染みて感じていました。そのため、新しい形の「共創」を模索し始めます。

「転機となったのは、小川さんが『ネイチャーポジティブ(生物多様性の損失を止め、反転させること)』を打ち出したときでした。同時期にシーベジタブルさんも一般社団法人グッドシーを立ち上げられ、お互いに目指すゴールが更新されたんです。そのとき、現場の技術ベースではなく、抽象度の高いところから見れば新しい可能性が見えるんじゃないかと思いました」。
当時、海藻養殖はすでに“やり切った”状態で、技術的な限界を迎えていると考えられていました。しかし、視座を上げ、別の領域からの視点で見たところ、まだ発展の可能性が残っていたことに気づきます。
「業界の中の人間にとって開発され尽くしたレッドオーシャンでも、外の我々の目で見ればまだ海は青かった。一次産業の常識に対し、我々二次産業の観点で見れば、もっと良くできる余地が残っていたんです。技術だけで見れば難しかった連携も、目的が変われば可能性はあるのだと気づきました」。
目的ありきではなく、そもそもの目的を描き、磨き上げるところからつながった両者。2024年11月に、海藻養殖を通じた社会課題の解決に向けた可能性を検討する共同実証契約を締結します。松村さんは、今回の共創について、次のように振り返りました。
「目的や目標を定め、足りないところが生じたときに外部と連携するやり方は、組み立てやすいのは確かで、間違ってはいないと思います。しかし、自分たちだけで描けるゴールには限界がある。我々はこれまで物売りの企業として、性能を上げたりコストを下げたりして、市場シェアをどれだけ獲得できるかで勝負してきました。今回、シーベジタブルさんと一緒に社会課題に挑んでいこうとしたとき、そうした視座で物事を見るのではなく、もっと違った観点でみる大切さに気付かされたんです」。
私たちがいなければ、生まれなかった共創を
社会課題の解決においては、理想的な人々の暮らしであったり、自然環境であったりと、技術的なスペックやコストとは異なる部分で勝負していく必要があります。そのためには、多種多様な人たち対話を重ねながら、一緒により良い社会とは何か、どうすれば社会課題を解決できるかについて考え、進めていくことが重要です。松村さんは、今回のシーベジタブルとの共創でその重要性に気付かされたと話します。
「今回のケースは、具体的にこうしよう、といった目的があって始まったものではありません。何か面白そうなことをしている人たちと出会い、一緒に取り組めばもっと面白くなりそうだとの予感があって、可能性を模索してきたことで今に至ります。我々だけでは描けなかった未来の景色を、彼らと一緒に歩むことで描ける可能性を感じています。
共同実証契約以降、社員食堂で海藻の食材試食会を実施したり、そこから社食業者の方が来てメニューに取り入れるかどうか検討してくれたりと、ネイチャーポジティブの文化は少しずつ広がってきました。技術的な部分はまだこれからではあるものの、テレビや新聞といったメディアに取り上げられる機会が増え、社会からの関心も集まってきました。
松村さんは、大企業とベンチャー企業の連携の形として、こうした共創モデルが選択肢の一つになり、広がっていくと嬉しいと語ります。パナソニックにおいても、今回の事例が先駆けとなり、後に続く事例が増えてほしいと期待を寄せます。
「一言でパナソニックと言っても、さまざまな事業があり、隣の隣の部署は何をしているのかわからないのが実情です。そうした境界を越境することで、社内リソースを把握し、多様なステークホルダーとの共創や広く社会で役立てる方法を模索し、コーディネートしていく人材が増えれば、もっと色んな新しい挑戦が生まれると思っています」。
「パナソニックは、企業文化として『上から言われたこと以外やりません』というタイプの社員は少ないんです。今回のシーベジタブルさんとの共創は、押っ取り刀で駆けつけた有志のメンバーで始まり、面白いことがあればやってみたいと前向きに考えている人が積極的に参画してくれました。今後彼らのような社員が中心になって、こうした動きをどんどん創り出してくれると嬉しいですね」。
大きな展望を語った後、「なんか綺麗事っぽくなっちゃったなあ」とはにかんで退室した松村さん。たとえ今は綺麗事に思えても、これから先、多様な人々が互いに夢を描き、手を取り合う姿が当たり前となったら……。その風景こそが「私たちがいなければ生まれなかった世界」なのかもしれません。
商品の販売終了や、組織の変更などにより、最新の情報と異なる場合がありますので、ご了承ください。

未来の働き方サポーターによるこの記事へのコメントを掲載しています。
※この記事へのコメントはまだありません。