働き方の変革を探求する: EX革新室の挑戦

パナソニック ホールディングス(株)(以下、パナソニックHD)に設立された「EX革新室」は、「Employee Experience(従業員体験)」の革新を通じて、仕事の成果と従業員のウェルビーイングを両立させる取り組みを行う組織だ。リンクアンドモチベーションの林さんが、EX革新室 リードリンクの福井さんに話を聞いた。
「働く」のランドスケープデザイナーという新たな視点
林: まず福井さんの役割について教えていただけますか?
福井: 私たちは「働く」のランドスケープデザイナーです。と自己紹介しています。目を閉じて10年後に職場がどのような景色になっていて欲しいか想像し、そこに向かって今日何ができるかを考え、その働き方やプロセスをデザインする仕事です。
林: EX革新室はどういう経緯で作られたのですか?
福井: 2021年7月に発足しました。パナソニックHDの執行役員である小川さんが直接室長を務めていて、組織のミッションは「目覚ましい技術開発の背景には素晴らしい仕事のやり方が伴う」という考え方に基づいています。パナソニックHD技術部門1,500人余りの働き方を変革することで、イノベーションの創出を加速させることを目指しています。
林: なるほど、働き方を変えることで成果も変わるという発想ですね。
福井: そうです。「やり方が違うから結果が違う」という信念のもと、これまでの仕事のプロセスや環境を根本から見直しているんです。

働き方の全体像を捉え直す
林: 「働き方改革」というと勤務時間の短縮とか在宅勤務とか、そういう話になりがちですが、EX革新室での捉え方は違うようですね。
福井: そうです。多くの企業では「働き方改革」というと勤務時間や働く場所の柔軟化などに焦点が当たりがちですが、私たちは「仕事の成果を最大化するための要素」として「環境」「プロセス」「関係」「人」「意味」という5つの要素から働き方を再定義しています。
林: 5つの要素について、もう少し詳しく教えていただけますか?
福井: 「環境」とは物理的な職場環境やITツール、人事制度や組織構造を含みます。「プロセス」には会議のやり方や評価の仕方などが含まれます。「関係」は人と人とのつながりや信頼関係、「人」はスキルや個性、「意味」は仕事の目的や自分が何のためにそれをしているのかという理解ですね。働き方という言葉は抽象度が高すぎて、時間短縮などの狭い文脈で捉えられがちなので、私たちはより包括的に捉えるようにしています。

探索と実験から生まれる新たな組織モデル
林: 実際にEX革新室ではどのような取り組みをされているのですか?
福井: まず、私たちの組織の運営方法自体が実験的なんです。従来のヒエラルキー型組織ではなく、「ホラクラシー」と呼ばれる自律分散型の組織運営を取り入れています。従来の組織では階層ごとに情報が伝達されますが、ホラクラシー型では必要な人が必要なときにつながり、それぞれのチームが自律的に動きます。
林: 最初から上手くいったのでしょうか?
福井: いいえ(笑)。最初の1年間は、私たちEX革新室自身がまず新しい働き方のモデルになろうと試みました。メンバー起案型のプロジェクト設計や、プロジェクト起案者なら誰でも予算執行権を持てる仕組みの導入、部署の壁を越えた兼務メンバーの活用などを実験的に行ってきたんですが、実践してみると課題も浮かび上がりました。思いのあるテーマが設定されオーナーシップは高まったものの、遠心力が強くなりすぎて全体としてのまとまりが欠けたり、予算管理にも課題が生じたりしたんです。
林: 失敗から学ぶことも大切ですね。
福井: そうなんです。試行錯誤を経て、私たちはどうすればこの学びを組織全体へ還元することができるのか、ということを考えました。そこで2年目からは「学びを実践する」フェーズへと移行し、オープンハウス形式のイベントなどを通じて組織外への働きかけを始めたんです。そして3年目となる今は「現場への実装」を目指す段階に入っています。

体験を通じた変化の連鎖をデザインする
林: 現場への実装はどのように進めておられるのですか?
福井: 私たちが行き着いた結論は、ノウハウを伝えるだけでは変化は起こらないということです。良い体験をしてもらうことが重要なんです。そのため、実際に部課長クラスの人材をターゲットに、新しい会議のやり方や働き方を体験してもらい、その体験が良かったと思えれば自分の職場に持ち帰ってもらうという戦略を採っています。
林: 今日のこの対談の場も工夫されていますよね。
福井: そうなんです!これらは「ミーティング・ガイドライン」に基づいたものです。通常の座席配置ではなく、自由度の高い空間で、グループサイズを変えながらディスカッションを行うことで、発言量や内容が変化することを体感してもらっています。コーヒーやお菓子の提供、場の転換など、細部にわたる工夫も盛り込んでいます。実際、私たちが最初に取り組んだのは会議のあり方でした。会議は組織文化が凝縮されているんですよ!
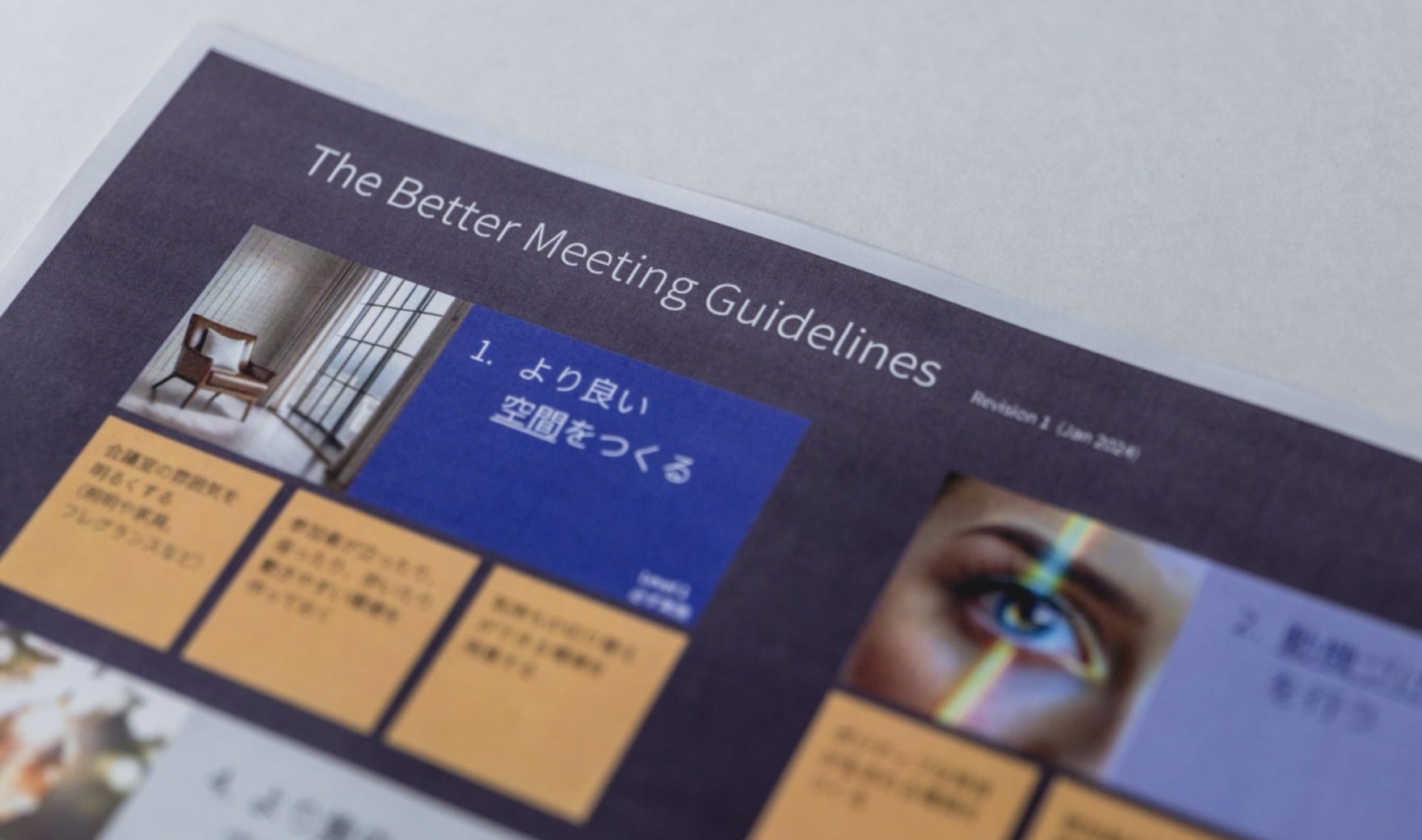
システム思考で自走する組織へ
林: 最終的にはどのような状態を目指しているのでしょうか?
福井: 意外かもしれませんが、私たちの最終的なゴールは「私たちEX革新室という組織自体が無くなること」です。専任の組織などなくとも、現場で自然とより良い働き方が生まれ続ける状態こそが健全な姿だと考えています。
林: そのためにどんなアプローチを取っているのですか?
福井: 私たちが採用しているのが「システム思考」のアプローチです。社内での活動や広報を通じて、人々が自発的に働き方を見直し、それが周囲に広がり、さらに新たな動きを生む—そうした好循環をデザインしています。単に施策を実施するのではなく、その裏側で起こることを設計しているんです。例えば広報誌を配ることで、知らない人同士が会話を始め、部門を超えた繋がりが生まれる。そういった相互作用のダイナミクスをデザインするのが私たちの役割です。
林: デザインの概念も進化しているんですね。
福井: 現代のデザインの潮流は、物のデザインから体験のデザイン、参加のデザインを経て、システムのデザインへと進化しています。「働く」のランドスケープデザイナーとは、「働く」という営み全体をシステムとして理解し、どこに力点を置けば好ましい変化が起きるかを設計する新しい職能なんです。

未来の働き方に向けて
林: パナソニックが目指す未来の技術と働き方の関係についてはどうお考えですか?
福井: 私たちの所属するパナソニックHD技術部門は「私たちがいなければ生まれなかった世界をつくる」というミッションを掲げていますが、これを実現するためには、これまでの働き方では限界があるという認識が根底にあります。パナソニックHD技術部門が掲げている技術未来ビジョンの思想に通じる「思いやりで繋がる社会」「日々の時間に生きがいが循環する世界」「心地よい状態で関係性が良くなる」といった新しい価値を生み出すには、働き方自体も革新する必要があります。
林: 3年間の活動を振り返っていかがですか?
福井: まだ道半ばだと感じています。しかし、私たちの取り組みは単なる働き方改革を超え、仕事と人の関係性を根本から問い直す壮大な実験だと思っています。結果の違いはやり方の違いから生まれる—その信念のもと、パナソニックの技術者たちと共に、仕事のやり方そのものを研究開発の対象とし、未知の領域を切り拓き続けていきたいですね。
林: 今日はありがとうございました。EX革新室の挑戦、これからも注目していきます。
福井: こちらこそありがとうございました。
商品の販売終了や、組織の変更などにより、最新の情報と異なる場合がありますので、ご了承ください。

未来の働き方サポーターによるこの記事へのコメントを掲載しています。
※この記事へのコメントはまだありません。